
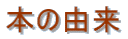
元来、「本」という漢字は、「物事の基本にあたる」という意味から転じて書物を指すようになった。
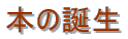
6世紀はじめにベネディクトゥスがイタリアに設けた修道院の修道士たちである。
25㎝×45㎝の羊皮紙を半分に折り、4枚ごとに咽に皮ひもを通してそれらを重ねて一冊にすると、ひもで山になった背ぐるみに皮をかぶせて表紙ができた。

15世紀半ばに、ドイツのヨハネス・グーテンベルクが金属による可動性の活字を使いぶどうしぼり機を利用した印刷機を操作して印刷術を興してから全く面目を改めた。
1455年以降グーテンベルクによって印刷された『グーテンベルク聖書』などによって印刷技術の意義が示されたことで印刷術は全欧州に広がり飛躍的な発展を遂げることとなった。

日本で作られた本和書は、洋書の歴史とは異なり、いきなり紙の本から始まった。
日本書紀によれば610年に中国の製紙術を日本に伝えたと言われ、現在残っている最古の本は7世紀初めの聖徳太子の自筆といわれる法華義疏であるとされている。
また、日本では製紙法の改良により、楮、三椏などですいた優れた紙の本が生まれている事も特筆すべき点である。
奈良時代の本の遺品は数千点にのぼり、1000年以上昔の紙の本がこれほど多数残されているのは世界に例がないほど!
※三椏・・・電気・ガス・水道などの配線・配管で、一本から二本に分ける部分で使う器具のこと。
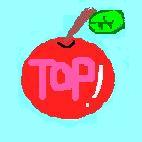
![]()