|
第18回九州マイクロウェーブ・ミーティングは,マイクロウェーブ筑後グループのお世話で4月14,15日に久留米市シーガルホテルで開催されました。
急な会場変更というアクシデントもありましたが,70名を越える参加がありました。
以下が2日目の発表内容の概要です。なお,次回は北九州,その次は長崎での開催が決定しました。
○ 秋月CSコンバータの10GHz改造(JA6JNR)
 JA6JNR渕OMが秋月電子通商で売られているCS LNBを56個購入し,10GHz ATVコンバータに改造して希望者に分けた。
このCS LNBは現在も秋月で500円で売られている。
JA6JNR渕OMが秋月電子通商で売られているCS LNBを56個購入し,10GHz ATVコンバータに改造して希望者に分けた。
このCS LNBは現在も秋月で500円で売られている。
・局部発振周波数 10.678GHz ねじで周波数可変。
・1st IF出力900から1800MHz。
改造方法
- 外蓋のネジをはずして外蓋を本体からはずす。
- 電波誘導体を本体からはずす。
- 局発部の蓋をはずす。
- 基板のネジを外して,基板を本体からはずす。
- 本体の入力部は縞状の構造になっているので,サンダで平らに削り,SMAコネクタをその跡に付ける。
- フィルタ(コの字型の形)に単線でL型に柱を立てる形でハンダ付けする。
- 局部発信の改造はフィルタに単線でL型にハンダ付けする。
- 本体に基板を取り付ける。
- 電源を加圧して局部発信の周波数が11.4GHzになるよう調整ネジで調整する。
- 入力部は基板とSMAを接続する。
 56個のうち75%が実用使用が可能だったとのことです。
この他に,10GHz帯・24GHz帯ATV用SG,24GHz帯ATV用ミキサーについて。
56個のうち75%が実用使用が可能だったとのことです。
この他に,10GHz帯・24GHz帯ATV用SG,24GHz帯ATV用ミキサーについて。
○ メーカ製移動体BS方送受信装置について(JA6FIV)
船舶用のBS方送受信装置を入手した。
電波の水平方向,垂直方向をセンサで感知し,アンテナ駆動装置により衛星を自動的に追尾するようになっている。
アンテナはダブレット約300本を合成してある。
○ 携帯電話は宝の山(JA6BI)
 携帯電話には,普通では入手困難なデバイスが数多く使われている。
その中で,デジタル方式の変調のために直交変調器が使われています。
調べてみると,SSBジェネレータそのものであり,技術的には昔からある技術である。
これを利用して1.2GHzや2.4GHz帯で直接SSBの変調が得られるかもしれない。
携帯電話には,普通では入手困難なデバイスが数多く使われている。
その中で,デジタル方式の変調のために直交変調器が使われています。
調べてみると,SSBジェネレータそのものであり,技術的には昔からある技術である。
これを利用して1.2GHzや2.4GHz帯で直接SSBの変調が得られるかもしれない。
リチウムイオン2次電池小型で大容量であるが,高価で市販では入手しがたい。
しかし,携帯電話にはリチウムイオン電池が使われており,ジャンクからこれを取り外して利用すると便利である。
内部の制御回路を取り外し,4.2V 1Aの定電圧,定電流で充電すればよい。
充電時は電池が並列に,使用時は直列になるようなスイッチを作っておくと便利である。
「青歯大王に噛まれたら痛い!?」
アマチュアバンドには,アマチュアだけでなく他の業務と共用するバンドがあり,ISM(Industrial, Scientific, Medical)バンドである2.4GHz帯もそのひとつである。
最近,2.4GHz帯では無線LANやBluetoothの電波が2.4GHzのハムバンドに多数出現しており,yama-mlでも伝えられたように,霞ヶ関の2.4GHzリピータにもその影響が現れている。
もし,逆にアマチュアがこれらに対して妨害を与え,訴追を受けた場合,どう対応したらよいであろうか。
電波法では混信を与えないことを確認して送信することになっているが,無線LANやBluetoothはスペクトル拡散方式であり,混信を確認することは困難である。従って,免許があり,免許された電力であれば,正当性を主張し,電波法違反での刑事罰は免れることはできるかもしれない。
しかし,民事で高額の損害賠償を請求される可能性もある。
このような場合,JARLは会員の救済をしてくれるのであろうか?
○ ドイツ製のマイクロウェーブ関連機器について(JA1EPK)
 昨年の初め頃から10名ほどが47GHz,75GHz,142GHz帯を始めた。
これらのバンドではアンチパラレルミキサーなどのミキサーが重要となってくる。
昨年の初め頃から10名ほどが47GHz,75GHz,142GHz帯を始めた。
これらのバンドではアンチパラレルミキサーなどのミキサーが重要となってくる。
○ 全国・関東地区のマイクロウェーブ活動について(JH1UGF)
 地域による情報格差の解消を目的にYAMA-mlを立ち上げた。
昨年は60名だったが,現在の登録者数は220名を越えている。
地域による情報格差の解消を目的にYAMA-mlを立ち上げた。
昨年は60名だったが,現在の登録者数は220名を越えている。
東京の2.4GHz帯は,無線LAN,ビル間通信,Bluetoothなどの妨害がいっぱい。
総務省情報通信審議会2.4GHz高度化方策委員会で利用の見直しが検討されることになっているが,最悪の場合アマチュアが排除される可能性もある。
5.6GHz帯においてもアメリカ製の5760MHz無線LANの輸入を求める圧力がある。
免許の数ではなく,タイマーでATVのビーコンを出すなど,運用実績を作ることが重要である。
ASAHIパソコン No.287 5.1号に「無線LAN vs. ブルートゥース徹底比較」として,P.34からP.47まで14頁にわたり掲載されている。
その中には,「2.4GHz帯は,特別な免許がなくても利用できる周波数帯である。
それだけに,いろんな電波が飛び交っており,通信の妨げになることがある。
身近なものでは,電子レンジもこの周波数帯を使う製品の一つだ。」‥‥‥とあるが,アマチュア無線で使用されているとの認識は無く,完全に無視されている。
AO-40が打ち上げられ,144MHz,430MHz対に加え,2.4GHzビーコン,5.6GHz,10.45GHz,24GHzのトランスポンダが搭載されている。
○ 最近のマイクロウェーブ動向について(JG1QGF)
 これまでに1000MHz以上で合計345MHz削減されている。
2.4GHz帯も関東では無線LANだらけで,LAN同士あるいはLANとアマチュア間での混信の影響が出てきている。
数の力でアマチュアが排除される可能性もある。
アマチュアは2次使用であり,リピータはビーコンを出すなどして使用をアピールする必要がある。
これまでに1000MHz以上で合計345MHz削減されている。
2.4GHz帯も関東では無線LANだらけで,LAN同士あるいはLANとアマチュア間での混信の影響が出てきている。
数の力でアマチュアが排除される可能性もある。
アマチュアは2次使用であり,リピータはビーコンを出すなどして使用をアピールする必要がある。
1エリアでは,47GHz,75GHzで毎週のように記録に挑戦している。
5GHz帯でも,高速道路のETC,移動体への情報提供をするITS次世代交通システム,カーフェリーや駐車場の料金徴収のESRC,76GHzのASVミリ波レーダーなど,今後影響してきそうなものがある。
○ 包括免許制度について(JA6AQ)
 昨年のミーティングで包括免許制度の署名を行ったそうだが,アメリカの包括免許をイメージしているようであるが,日本の包括免許とはMCAや携帯電話など,他から制御される無線局のものであり,アメリカの制度とは全く異なるものである。
アメリカでは従事者免許と無線局免許が包括されており,上級局でも執行した場合,ノビスから再受験しなければならないなど,厳しい面もあることを知ってもらいたい。
昨年のミーティングで包括免許制度の署名を行ったそうだが,アメリカの包括免許をイメージしているようであるが,日本の包括免許とはMCAや携帯電話など,他から制御される無線局のものであり,アメリカの制度とは全く異なるものである。
アメリカでは従事者免許と無線局免許が包括されており,上級局でも執行した場合,ノビスから再受験しなければならないなど,厳しい面もあることを知ってもらいたい。
東京練馬 JA1AKA 荒川 賢
 5月11日の午後の便で羽田から大分空港まで行きました。
荷物がかなりあって大変でしたが,なんとか九州にたどりつきました。
5月11日の午後の便で羽田から大分空港まで行きました。
荷物がかなりあって大変でしたが,なんとか九州にたどりつきました。
11日はホテルに長屋さんと木本さんが訪ねてこられて,誘われて古い別府の温泉街を散歩したり,夕ご飯をご馳走になったりしました。
翌12日朝7時にJI6DRF大橋さんが迎えにきて,車で国東半島のほぼ中央にある両子寺に行き,和尚さんのJA6TM 応利さんにお会いしました。
この日ATVを運用する両子山は頂上まで道路はありますが,ゲートをこの両子寺で管理している関係で大橋さんと応利さんのお陰で山頂まで車で登ることができました。
高さが721mのこの山頂はこの日天気が良かったので,見晴らしがFBでした。
ATVは1200MHzと2400MHzと10.1GHzと10.45GHzと24GHzで大分,別府のATVグループと北九州ATVグループとFBにQSOができました。
24GHzまでのATV QSOが終わり,物凄い急坂に大橋さんに命を預けて両子寺で再度応利OMにお会いしてお礼を言ってから別府に戻り,別府と大分の中間地点の海岸に近いところで47GHz ATVの伝播実験をやりました。
予想していた通り少してこずりましたが,47GHz ATVの伝播実験にも成功しました。
翌13日は朝6時半にJA6SPI穴見さんが迎えにきてくれました。
お天気の良い朝のドライブは快適で,山登りなんか止めたくなりました。
牧の戸峠で穴見さんとお別れしてひとり淋しく重い機材をしょつて登山を開始しました。
天気が良過ぎるのと肩の荷が重いので予定時間の10時を22分遅れで山頂に達しました。
天気も良く,早速設営をして1200MHzと2400MHzと10.1GHzのATVを開始しました。
平成森林公園移動の大分,別府のATVグループとは前記周波数全部で,天山移動のATV局と熊本のATVグループとは1200MHz ATVでFBなQSOができました。
ただ,残念なのは五家原が岳移動の長崎ATVグループとは1200MHzと2400MHzで当方にてM5Cで受像できた1Way QSOに終わりました。
15時に下山開始,登るのにかなりエネルギーを費やしているのとこの日泊まる法華院温泉山荘(山小屋)は山奥の温泉で,そこに行くには急な岩場を通過しなければならず,片手にパラボラアンテナを持っているため岩登り(岩下り)の基本である三点支持がてきず,苦労して下りました。
夕方,山荘に着きましたが膝,腰がガクガクになりました。
少し休んでからぬるめの温泉に長い時間浸かりました。
翌日はバスの関係で,昨日下った急な岩場をまた登りました。
普通3時間20分で行けるところを休み休み4時間近くをかけて登り,下りました。
途中の分技点で聞いた話ではここは良く遭難するところで四,五日前にも近くで二体の白骨がみつかったそうですが,どうしてこんなところで遭難するのか私には不可解でした。
再度足腰をガタガタにして牧の戸峠にもどりバスで湯布院に出て街を見物,みやげものを買って特急で博多に出てここでも街を見物,名物の博多ラーメンを食べ,20分遅れの羽田行きの飛行機に乗りました。
台風の接近で一万メートル付近の揺れが大き目でした。
自宅には丁度23時に着きました。
夜足が痛くて眠れず,バンテリンを塗って睡眠薬をのんでやつと眠りました。もうこんな無理をするのは止めようと思ってから数年が経ちました。
九州の人がこんな良いお天気はめずらしいというほどの好天に恵まれ,さらに良いATV仲間に恵まれて私は運が良いのだと思います。
でもちょつと注意しないといけないかなとも思います。
年には勝てないと再度自覚する移動でした。
お世話になった九州のアマチュア無線の皆さん有難うございました。
JA6DM 於保 武志
長崎グループは,JA1AKA荒川さんが九州へ移動された5/12と5/13のうち,5/12の両子山と五家原岳間は途中にいくつかの高い山があり見通し外でQSOの可能性がないので移動しませんでしたが,5/13は五家原岳へJA6DT,JA6COK,JA6EQC,JA6FIV,JA6IDZ,JA6RMG,JH6GTR,JF6BUG,JA6DMの9局が登りました。
 久住山移動の荒川さんとは,1.2GHz,2.4GHz,10GHzとも全員受信がNGでした。
送りは,1.2GHzと2.4GHzは久住山でやっと色がつく程度で受信できていたそうです。
五家原岳から久住山方向は,眼下は海で障害物はなさそうで,大分のJA6LXR長屋OMにお願いして事前にカシミールで見通しを確認してもらっていたし,距離も約110kmで見通しなので,私はいつもなら1.2GHzや2.4GHzでもパラボラを使用していたのですが安心して,1.2GHzは17エレGIP八木,2.4GHzは32エレGIP八木を使用したのが失敗だったのかもしれません。
他の局も1.2や2.4は八木ANTでしたが全局が受信がNGでした。
NGの原因ははっきりしません‥‥少しは山頂のサテ局のかぶりがあったかもしれません?が,連絡用の430MHz ANTは,マスプロの15エレ八木でしたので,連絡はバッチリでしたが。
久住山移動の荒川さんとは,1.2GHz,2.4GHz,10GHzとも全員受信がNGでした。
送りは,1.2GHzと2.4GHzは久住山でやっと色がつく程度で受信できていたそうです。
五家原岳から久住山方向は,眼下は海で障害物はなさそうで,大分のJA6LXR長屋OMにお願いして事前にカシミールで見通しを確認してもらっていたし,距離も約110kmで見通しなので,私はいつもなら1.2GHzや2.4GHzでもパラボラを使用していたのですが安心して,1.2GHzは17エレGIP八木,2.4GHzは32エレGIP八木を使用したのが失敗だったのかもしれません。
他の局も1.2や2.4は八木ANTでしたが全局が受信がNGでした。
NGの原因ははっきりしません‥‥少しは山頂のサテ局のかぶりがあったかもしれません?が,連絡用の430MHz ANTは,マスプロの15エレ八木でしたので,連絡はバッチリでしたが。
天山移動の唐津のJA6DML吉田さんや,ホームシャックからの佐賀県牛津町JA6BLS滝本さん,福岡県柳川町JA6CWQ馬場さんとはM5CでQSO出来ましたが,久住山移動のJA1AKA荒川さんとはATVが2WAYではなく片側QSOになったのが残念でした。
鹿児島県移動のJA6TY玉利さんとJH6EKW竹宮さんとは,2.4GHzのF3では59+でしたが時間の都合でATVではQSO出来ませんでした。
JA1AKA荒川さんは,一人で久住山山頂まで3バンドのATV機材を担ぎ上げ大変苦労様でした。
又,来年でも九州へ移動された時はATVでの2WAY QSOを楽しみにしております。
無線LANやBluetoothで用いられているスペクトル拡散(SS)通信方式とはどんなものか,ホームページで調べてみました。
スペクトル拡散通信方式では,干渉波の排除能力が著しく高く,他の利用者の信号と周波数が重なっても,拡散符号系列(一種のパスワードみたいなもの)を変えることによって混信のない通信が実現できるといわれています。
SSには,DS(直接拡散)方式,FH(周波数ホッピング)方式,これらを組み合わせたハイブリッド方式があります。
無線LANで用いられているDS方式は,情報信号に1次変調を施した後に情報伝送速度よりも十分に速い拡散符号で2次変調をかけ,広帯域に拡散し,情報1ビットあたりの電力密度を小さくして送信するものです。
受信側では,同じ拡散符号をかけて逆拡散することにより元のデータを復元します。
「スペクトル拡散」「逆拡散」は,PN(Pseudo-random Noise:疑似雑音)符号という特殊な符号を掛け合わせるという動作になります。
PN符号は,デジタル変調波と同じく2つの値をとりますが,その変化の周期はデジタル変調波のものよりも一定以上速く変化するようにしてあります。
ここで,デジタル変調波の変化のスピードは「ビットレート」,PN符号のスピードは「チップレート」と呼んでいます。また,ビットレートとチップレートとの比を「拡散率」といいます。
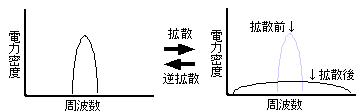 このようにして信号を掛け合わせると,信号の「電力密度スペクトル」が大きく変化し,電力密度スペクトルが薄く広く分布します。
スペクトル拡散の前後における信号の周波数帯域の比は,拡散率にほぼ一致します。
このようにして信号を掛け合わせると,信号の「電力密度スペクトル」が大きく変化し,電力密度スペクトルが薄く広く分布します。
スペクトル拡散の前後における信号の周波数帯域の比は,拡散率にほぼ一致します。
この信号は,適当なタイミングで,かつ送信側で使ったものと同じPN符号を使って逆拡散したときのみ,スペクトル拡散をする前の信号に戻せます。
ユーザごとに拡散符号を割り当てれば,複数のユーザが同時に接続できます。
このため,伝送路において干渉成分や雑音が重畳されても,受信側で復調時に 逆スペクトル拡散を行うことによって,復調された信号成分に比べて絶対レベルが十分小さくなるため,干渉や雑音の影響を受けにくいという特徴があります。
無線LANシステムでは,ESS-ID(Extended Service Set Identity)とかGroup-IDとかを個別に設定することでネットワークを分離しています。
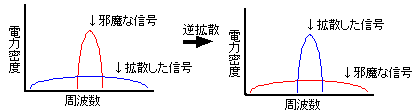 スペクトル拡散と逆拡散は,全く同じ動作です。送信から受信までの間に邪魔な信号が割り込んできても,逆拡散の際に邪魔な信号は「スペクトル拡散」されます。
そこで,適当な周波数帯の信号だけを取り出すようにしておけば,必要な信号だけが首尾よく取り出せ,送信から受信までの間に割り込んできた邪魔な信号を排除できるという利点があります。
スペクトル拡散と逆拡散は,全く同じ動作です。送信から受信までの間に邪魔な信号が割り込んできても,逆拡散の際に邪魔な信号は「スペクトル拡散」されます。
そこで,適当な周波数帯の信号だけを取り出すようにしておけば,必要な信号だけが首尾よく取り出せ,送信から受信までの間に割り込んできた邪魔な信号を排除できるという利点があります。
一方,Bluetoothで採用されているFH方式は,2次変調として複数の周波数をある規則に従って順次切り換える(ホッピング)することにより,周波数相関の低い信号を得ます。
この方法では,ホッピングする周波数の順序がユーザごとに異なり,これを各ユーザに割り当てれば,複数のユーザが同時に接続できます。
周波数変換のパターンは「ホッピングパターン」といい,このパターンに従って周波数変換を行うと,傍目には搬送波周波数がランダムかつ広い範囲で飛び回るようになります。
周波数ホッピングを行うと,周波数スペクトルは下図のようになります。
なお,この図は周波数スペクトルを長い時間観測したときの平均をとったもので,それぞれの山は,別々のタイミングで発生したものです。
信号スペクトルの形はDS方式のものと多少違いますが,元の信号より周波数帯域が広がり,電力密度の薄い信号に変換するという点ではよく似ています。
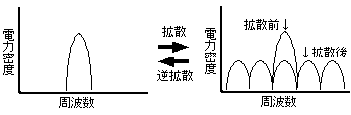 FH方式の動作は,DS方式のPN符号がホッピングパターンに置き換わったようなもので,逆拡散も直接拡散方式と似たようなことを行います。
元の信号を取り出すには,受信した信号を送信したときと同じホッピングパターンを使って周波数変換をかけます。
この場合,ホッピングパターンと周波数変換のタイミングが一致したときのみ元の信号が取り出せます。
FH方式の動作は,DS方式のPN符号がホッピングパターンに置き換わったようなもので,逆拡散も直接拡散方式と似たようなことを行います。
元の信号を取り出すには,受信した信号を送信したときと同じホッピングパターンを使って周波数変換をかけます。
この場合,ホッピングパターンと周波数変換のタイミングが一致したときのみ元の信号が取り出せます。
http://www.cis.ohio-state.edu/~jain/index.html,他
無線LAN(Melco製)を使ってアマチュアの影響を調べてみました。
無線LANのカードを取り付けたノートパソコンを,2.4GHz FM-TVおよびF3で送信中のアンテナのすぐ側に置いてみましたが,データ伝送速度にほとんど影響はありませんでした。
11Mbpsモードでは14ch(2484MHz)を使用していたためかなと思います。
同じように電子レンジから1mほどのところでやってみましたが,こちらでは無線LANは全く使用できない状態でした。
|

 5月11日の午後の便で羽田から大分空港まで行きました。
荷物がかなりあって大変でしたが,なんとか九州にたどりつきました。
5月11日の午後の便で羽田から大分空港まで行きました。
荷物がかなりあって大変でしたが,なんとか九州にたどりつきました。 久住山移動の荒川さんとは,1.2GHz,2.4GHz,10GHzとも全員受信がNGでした。
送りは,1.2GHzと2.4GHzは久住山でやっと色がつく程度で受信できていたそうです。
五家原岳から久住山方向は,眼下は海で障害物はなさそうで,大分のJA6LXR長屋OMにお願いして事前にカシミールで見通しを確認してもらっていたし,距離も約110kmで見通しなので,私はいつもなら1.2GHzや2.4GHzでもパラボラを使用していたのですが安心して,1.2GHzは17エレGIP八木,2.4GHzは32エレGIP八木を使用したのが失敗だったのかもしれません。
他の局も1.2や2.4は八木ANTでしたが全局が受信がNGでした。
NGの原因ははっきりしません‥‥少しは山頂のサテ局のかぶりがあったかもしれません?が,連絡用の430MHz ANTは,マスプロの15エレ八木でしたので,連絡はバッチリでしたが。
久住山移動の荒川さんとは,1.2GHz,2.4GHz,10GHzとも全員受信がNGでした。
送りは,1.2GHzと2.4GHzは久住山でやっと色がつく程度で受信できていたそうです。
五家原岳から久住山方向は,眼下は海で障害物はなさそうで,大分のJA6LXR長屋OMにお願いして事前にカシミールで見通しを確認してもらっていたし,距離も約110kmで見通しなので,私はいつもなら1.2GHzや2.4GHzでもパラボラを使用していたのですが安心して,1.2GHzは17エレGIP八木,2.4GHzは32エレGIP八木を使用したのが失敗だったのかもしれません。
他の局も1.2や2.4は八木ANTでしたが全局が受信がNGでした。
NGの原因ははっきりしません‥‥少しは山頂のサテ局のかぶりがあったかもしれません?が,連絡用の430MHz ANTは,マスプロの15エレ八木でしたので,連絡はバッチリでしたが。 JA6JNR渕OMが秋月電子通商で売られているCS LNBを56個購入し,10GHz ATVコンバータに改造して希望者に分けた。
このCS LNBは現在も秋月で500円で売られている。
JA6JNR渕OMが秋月電子通商で売られているCS LNBを56個購入し,10GHz ATVコンバータに改造して希望者に分けた。
このCS LNBは現在も秋月で500円で売られている。

 携帯電話には,普通では入手困難なデバイスが数多く使われている。
その中で,デジタル方式の変調のために直交変調器が使われています。
調べてみると,SSBジェネレータそのものであり,技術的には昔からある技術である。
これを利用して1.2GHzや2.4GHz帯で直接SSBの変調が得られるかもしれない。
携帯電話には,普通では入手困難なデバイスが数多く使われている。
その中で,デジタル方式の変調のために直交変調器が使われています。
調べてみると,SSBジェネレータそのものであり,技術的には昔からある技術である。
これを利用して1.2GHzや2.4GHz帯で直接SSBの変調が得られるかもしれない。 昨年の初め頃から10名ほどが47GHz,75GHz,142GHz帯を始めた。
これらのバンドではアンチパラレルミキサーなどのミキサーが重要となってくる。
昨年の初め頃から10名ほどが47GHz,75GHz,142GHz帯を始めた。
これらのバンドではアンチパラレルミキサーなどのミキサーが重要となってくる。
 地域による情報格差の解消を目的にYAMA-mlを立ち上げた。
昨年は60名だったが,現在の登録者数は220名を越えている。
地域による情報格差の解消を目的にYAMA-mlを立ち上げた。
昨年は60名だったが,現在の登録者数は220名を越えている。 これまでに1000MHz以上で合計345MHz削減されている。
2.4GHz帯も関東では無線LANだらけで,LAN同士あるいはLANとアマチュア間での混信の影響が出てきている。
数の力でアマチュアが排除される可能性もある。
アマチュアは2次使用であり,リピータはビーコンを出すなどして使用をアピールする必要がある。
これまでに1000MHz以上で合計345MHz削減されている。
2.4GHz帯も関東では無線LANだらけで,LAN同士あるいはLANとアマチュア間での混信の影響が出てきている。
数の力でアマチュアが排除される可能性もある。
アマチュアは2次使用であり,リピータはビーコンを出すなどして使用をアピールする必要がある。 昨年のミーティングで包括免許制度の署名を行ったそうだが,アメリカの包括免許をイメージしているようであるが,日本の包括免許とはMCAや携帯電話など,他から制御される無線局のものであり,アメリカの制度とは全く異なるものである。
アメリカでは従事者免許と無線局免許が包括されており,上級局でも執行した場合,ノビスから再受験しなければならないなど,厳しい面もあることを知ってもらいたい。
昨年のミーティングで包括免許制度の署名を行ったそうだが,アメリカの包括免許をイメージしているようであるが,日本の包括免許とはMCAや携帯電話など,他から制御される無線局のものであり,アメリカの制度とは全く異なるものである。
アメリカでは従事者免許と無線局免許が包括されており,上級局でも執行した場合,ノビスから再受験しなければならないなど,厳しい面もあることを知ってもらいたい。
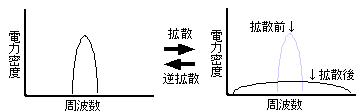 このようにして信号を掛け合わせると,信号の「電力密度スペクトル」が大きく変化し,電力密度スペクトルが薄く広く分布します。
スペクトル拡散の前後における信号の周波数帯域の比は,拡散率にほぼ一致します。
このようにして信号を掛け合わせると,信号の「電力密度スペクトル」が大きく変化し,電力密度スペクトルが薄く広く分布します。
スペクトル拡散の前後における信号の周波数帯域の比は,拡散率にほぼ一致します。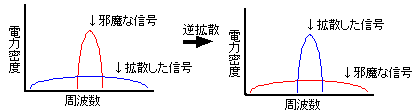 スペクトル拡散と逆拡散は,全く同じ動作です。送信から受信までの間に邪魔な信号が割り込んできても,逆拡散の際に邪魔な信号は「スペクトル拡散」されます。
そこで,適当な周波数帯の信号だけを取り出すようにしておけば,必要な信号だけが首尾よく取り出せ,送信から受信までの間に割り込んできた邪魔な信号を排除できるという利点があります。
スペクトル拡散と逆拡散は,全く同じ動作です。送信から受信までの間に邪魔な信号が割り込んできても,逆拡散の際に邪魔な信号は「スペクトル拡散」されます。
そこで,適当な周波数帯の信号だけを取り出すようにしておけば,必要な信号だけが首尾よく取り出せ,送信から受信までの間に割り込んできた邪魔な信号を排除できるという利点があります。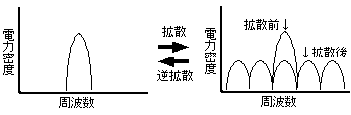 FH方式の動作は,DS方式のPN符号がホッピングパターンに置き換わったようなもので,逆拡散も直接拡散方式と似たようなことを行います。
元の信号を取り出すには,受信した信号を送信したときと同じホッピングパターンを使って周波数変換をかけます。
この場合,ホッピングパターンと周波数変換のタイミングが一致したときのみ元の信号が取り出せます。
FH方式の動作は,DS方式のPN符号がホッピングパターンに置き換わったようなもので,逆拡散も直接拡散方式と似たようなことを行います。
元の信号を取り出すには,受信した信号を送信したときと同じホッピングパターンを使って周波数変換をかけます。
この場合,ホッピングパターンと周波数変換のタイミングが一致したときのみ元の信号が取り出せます。